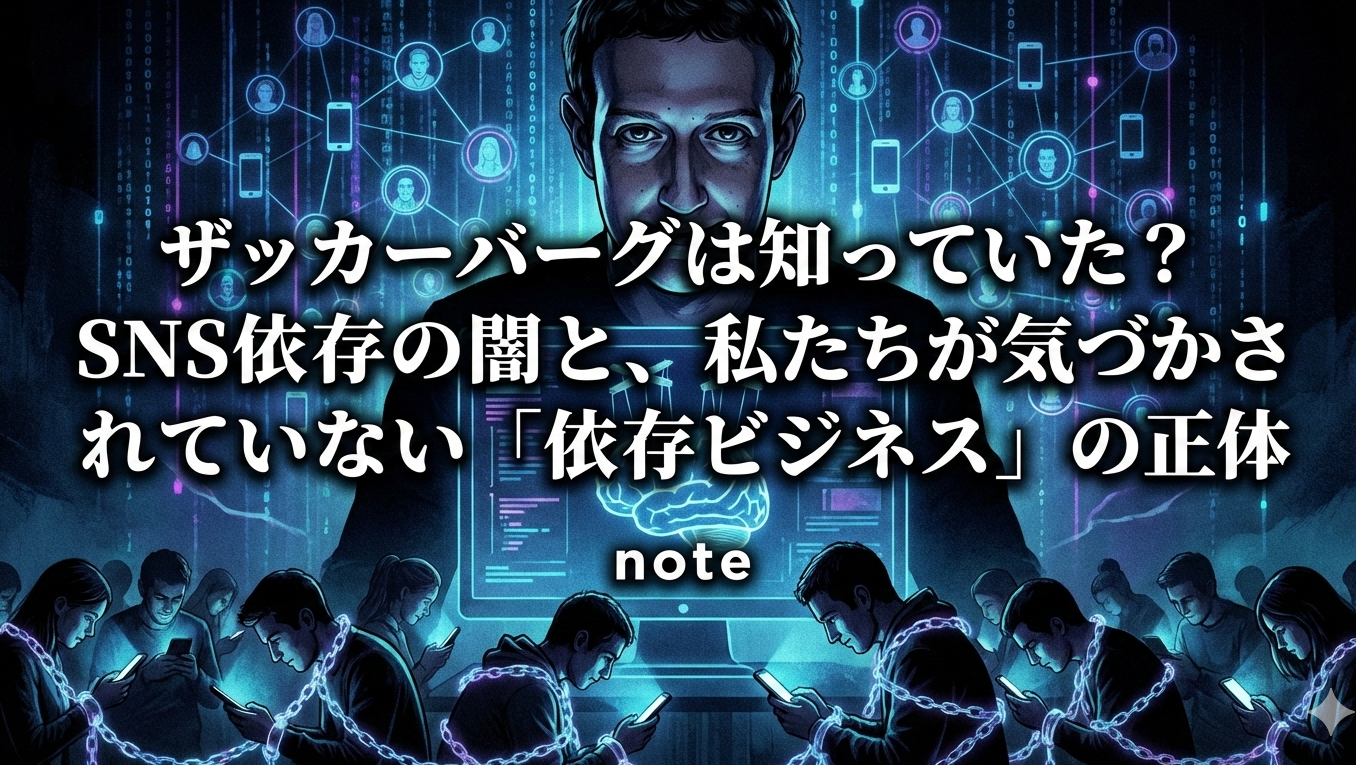子どものメンタルヘルスが壊されていく——そんな訴えを持った親たちが、ついにMeta社を法廷に引きずり出した。ソーシャルメディアへの依存が子どもたちに深刻な影響を与えているとして起こされたこの集団訴訟は、単なる企業対消費者の戦いではなく、現代社会の構造そのものへの問いかけとも言える。
Metaの内部告発者、フランシス・ホーゲンがかつて暴露したように、同社はInstagramが10代の少女の自己イメージを傷つけることを社内調査で把握しながら、それを公表せずにサービスを拡大し続けた。アルゴリズムは「滞在時間」を最大化するよう設計されており、不安や怒り、羨望を煽るコンテンツほどよく拡散される仕組みになっている。陰謀論的に聞こえるかもしれないが、これは陰謀ではなくビジネスモデルだ。ユーザーの感情を燃料にして、広告収益が生まれる。子どもだって、そのエンジンの一部にすぎない。
SNSでの反応は真っ二つに割れている。「スマホを与えたのは親でしょ」という声と、「プラットフォームに規制を」という声が激しくぶつかり合う。どちらも間違ってはいない。ただ、この議論の構図自体が巧妙で、責任をユーザー側に押し付けることで、プラットフォーム企業が批判をかわしてきた歴史がある。タバコ産業がかつて「吸うかどうかは個人の自由」と言い続けたように。
ここで視野を広げると、依存ビジネスは何もSNSに始まった話ではない。超加工食品に大量に含まれる砂糖・脂質・塩分の組み合わせは、脳の報酬系を刺激するよう科学的に最適化されている。食品メーカーが「もっと食べたくなる」配合を意図的に研究してきたことは、内部文書によって明らかになっている。そしてさらに遡れば、宗教もまたコミュニティへの帰属感、罪と赦しのサイクル、来世への希望といった心理機制を通じて、人々を強力に結びつけてきた。それが支配のツールになった歴史も否定できない。
依存させることで人を動かす——これは人類が権力を維持するために使い続けてきた最も古い手法のひとつだ。現代においてその手法が、テクノロジーという洗練された形をまとって再登場しているにすぎない。
今回の訴訟が業界全体の安全基準を変えるきっかけになるかもしれない。だが本質的な問いはもっと根深い。私たちは「何かに依存させられることで、誰かが得をする社会」に生きていないか? ザッカーバーグを法廷に立たせることより、その構造に気づくことの方が、ずっと革命的かもしれない。